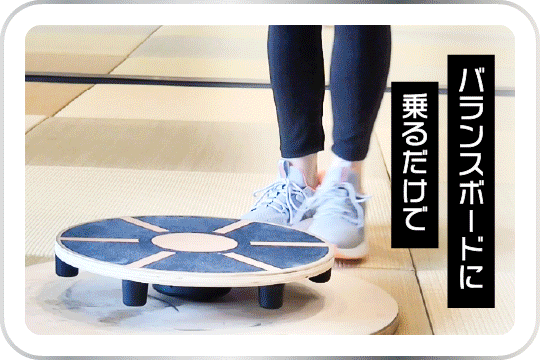RCC中国放送 「元就。外伝」番組内で紹介されました
be reported in the media

▲《免疫力向上》がテーマの白竜湖リゾート内にある、
ワタナベバランスジムで採用されています!
▲アンガールズ田中さんにも 乗っていただきました!



\ ついに、動的バランスをかんたんに楽しく評価できるツールが新登場 /


【1分54秒】でバランスコアがわかる! 紹介動画はこちら
こんな課題ありませんか?
Do you have any of these problems?
▼あなたの事業のタブをクリック▼


楽しみながら「バランス力」をアップできる
レクリエーションを取り入れたい
バランス評価の客観的な計測・アドバイスができていない
転倒予防につながる、効果的な対策を行いたい
リハビリ意欲を高めたい
その課題、
BalanScoreで解決!
バランスコア 5つの特長


Three features of BalanScore
01

バランス力が得点表示されるので
ゲーム感覚で楽しい!
バランスボードに乗ります。
「ピッピッピー」を合図に計測スタート。身体の傾きが画面に表示されて・・・
15秒後、あなたのバランス力の得点が出ます!
みんなで競争・挑戦したくなること間違いなし!
03

バランス改善トレーニングの
モチベーションUP!
「続かない・・・」トレーニングって通常そうですよね。
人は「報酬」が無いと脳の線条体(せんじょうたい)という意思決定を司る部位が活性化されず、やる気が起きないことが研究で証明されています。ですが、ゲームになると、途端にやりたくなりますよね。楽しい!と思った時に脳内で興奮物質のドーパミンが出るから、続けにくいバランス改善トレーニングもモチベーションがアップします!
05

マーカーなど身体への装着ゼロ!
誰でも簡単!
身体へ何か着けないといけない?
いいえ、必要ありません!
バランスボードの裏面に取付けるオリジナルセンサモジュールからBluetoothでパソコンへ自動的にデータが送信されるので、身体に何か装着する準備はありません。ですので、スタッフへの専門的教育も必要なく誰でも簡単に始められます。「使いこなせるか心配」ということは無いのでご安心ください。
02

バランス力の客観的評価ができて
信頼性アップに!
「足場が不安定な状態で足を動かさずに、どのくらいバランスを保てますか…?」それを簡単に測るものは今までありませんでした。
ですがバランスコアを使えば、動きを伴いながらも転倒しない状態を保つ=《動的バランス力》を知ることができます!
例えばパーソナルトレーニングの場合ですと、トレーナーの「主観」に頼ることなく測定結果にもとづいて「客観的」な評価ができるため、よりアドバイスの信頼性もあがるでしょう。
04

省スペースで女性でも軽いから
持ち運びもOK!
例えば、大型で重量のある健康管理機器だと移動は大変ですよね?
BalanScoreのバランスボードは《直径約39.5センチ×高さ8センチ》の大きさで約1.5kg(モジュール込)の軽さ。1.5リットルのペットボトルと同じ重さなので、女性でも移動は簡単です。
あとは評価システムインストール済みのPCさえあればスタートできるので「移動型サービス」でも、「場所を急に変更したい」なんて時もスムーズです!
こんな施設でご活用いただけます
in a scene like this
介護施設 や リハビリ施設、
「介護予防」や「健康寿命を延ばす」をコンセプトにしたイベントにも!
「バランス改善」をみんなで楽しく♪できる環境を作りませんか?


介護施設(養老ホームなど)
・リハビリ施設
●「転倒予防」の対策に
●楽しめるレクリエーションの提供
●バランス改善の客観的評価
整骨院/予防歯科
●バランス力の客観的指標による
アドバイスで、信頼性のアップに


専門学校
●バランス力の測定・強化
●講習・研究の利用にも
スポーツジム
●バランス力の客観的アドバイス
●シニア層向けコンセプトの強化に
●「バランス力トレーニング」対策


フィットネス
●みんなで楽しくバランス改善に
●シニア層向けコンセプトの強化に
●移動型フィットネスでも使える
まずは試してみないと分からない」という方に!
無料貸出サービスやっています
\今なら/
\ 下記一式を 2週間無料でお試しいただけます! ぜひ試してみてください /
貸し出し可能な台数には限りがあります。先着順となりますのでお早めに。

貸し出しセット内容
オリジナルバランスボード
1台
計測センサモジュール
(※バランスボード裏面に取付け)
1個
ノートパソコン
(※バランス評価システムインストール済み)
1台
※バランスボードは、バランスが不安定な状態です。付属の取り扱い説明書の注意事項をよくお読みいただき使用時には十分にご注意ください。
貸し出した際の事故や怪我、破損、トラブルについては、一切の責任を負いません。
\ ご不明な点やご相談などありましたら、こちらまで /
082-208-0866
[ 営業時間 9:00~18:00 ]
あなたも こんな経験ありませんか?


実は… 要介護が必要になった原因の
12.5%が「骨折・転倒」です

厚生労働省による「2019年 国民生活基礎調査」によると(2022年現在、最新となるデータ)、要介護者の介護が必要になった主な原因について、認知症が18.7%と最も多いですが「骨折・転倒」も4番目の多さで12.5%の割合を占めています(注1)。
しかも高齢者の転倒は大腿骨骨折や頭部外傷等につながることも多くあるそうです。
さらには、「また転倒したらどうしよう…」という恐怖から運動不足や生活不活発病(せいかつふかっぱつびょう)(注2)に結びつき、さらに①バランス能力低下 → ②骨折 → ③寝たきりという“悪循環”が生まれてしまう・・・ということなので注意が必要ですよね。
注1)参考:
令和元年 国民生活基礎調査(厚生労働省)>統計表 > 第15表 現在の要介護度別にみた介護が必要となった主な原因の構成割合 ※「介護」は、大規模調査年のみ実施。,2022年11月 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa19/dl/06.pdf
注2)生活不活発病とは:
「動かない」状態が続くことにより、心身の機能が低下して「動けなくなる」こと。別名【廃用症候群】。例えば避難所での不自由な生活ではなりやすいので注意が必要。似たような症状にロコモティブシンドローム(運動器が障害を起こし移動機能の低下をきたした状態)、通称ロコモ、がある。
高齢者の約8割超は「ころぶ」事故、
「転倒・転落・墜落」による死亡者数は「交通事故」の4.025倍!
もっと驚く事実かもしれないのですが、
東京消防庁のデータによると、高齢者が救急搬送されたもの《平成27年からの5年間》のうちで約8割以上は「ころぶ」事故(注3)とのこと。
こんなに多くの高齢者が「ころぶ」事故でケガをして救急搬送されているなんて、『本当?』って思ってしまいますよね。令和2年には55,183人(注3)が救急搬送されたそうです。
死亡者数でみてみますと、「令和二年人口動態統計(厚生労働省)」によれば《高齢者の転倒・転落・墜落による死亡者数》は8,851人(注4)。これは交通事故による死亡者数の4倍以上(注4)にもなる数なんだそうです。
注3)参考:
東京消防庁ホームページ(救急搬送データからみる高齢者の事故),2022年11月 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/topics/nichijou/kkhansoudeta.html

注4)参考:
消費者庁(高齢者の事故を防ぐために)>転倒 ,2022年11月 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_055/
令和2年人口動態調査(厚生労働省)によると、高齢者の交通事故による死亡者数が2,199人に対して、転倒・転落・墜落による死亡者数は8,851人。
人生100年時代に・・・
「転倒」は社会問題に発展しています

10月10日は「転倒予防の日(注5)」ということ、ご存知でしょうか?
これは、日本転倒予防学会が提唱されたそうなのですが、厚生労働省と消費者庁も日本転倒予防学会と協力して「転倒予防の日」を契機に、国民に対する転倒予防の呼びかけを行うことにしたそうです(注6)。
高齢者が元気に活躍するために予防対策が求められ、2022年4月には日本転倒予防学会が一般社団法人化されていることからも、今後ますます「転倒予防」は重要な課題になっていくと予想されます。
さらには、職場での転倒災害でも50代以上の女性で多く発生しているとのこと。一方で「自分はまだ高齢者でないから関係ない」という意識も多く、その乖離・ハードル・溝を社会環境全体で埋めていく必要があるのではないでしょうか。
注5)参考:
消費者庁(10(てん)月10(とう)日は「転倒予防の日」、高齢者の転倒事故に注意しましょう!) ,2022年11月
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_040/assets/consumer_safety_cms204_201008_01.pdf
注6)参考:
厚生労働省(10月10日は「転倒予防の日」、職場での転倒予防に取り組みましょう!) ,2022年11月https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21393.html
つまり
「転倒」を若いうちから「予防」することが
必須となる時代へ
-- 未来の子ども達のためにもなる ヘルスケア --



注7)参考:
博報堂生活総合研究所(シルバー30年変化)調査結果を発表 ~ 1986年 → 1996年 → 2006年 → 2016年 ~ ><気持ち年齢>は、「実年齢-14歳」,2022年11月
https://www.hakuhodo.co.jp/uploads/2016/06/20160624-2.pdf

(注7)
では、転倒しないために何が効果的?
Q.

例えば“段差をなくす”のような「外的要因」ではなく、「内的要因=身体づくり」の中で正しいトレーニングは?

A.
もちろん筋力も大切ですが同時に
《バランス力を改善すること》が効果的と言われています。
はい!実は
「筋力トレーニングだけ」は間違いなんです。


自分の転倒リスクを正しく知って
バランス機能を改善することは
【 健康寿命をのばす 】ことへつながります!

でも…
『本当なの?』『もっと詳しく聞きたい』
と思われますよね

その辺りを「専門家」へお伺いしました!
このバランスコアは
「姿勢調整機能」を研究されてきた専門家と
一緒に開発したものなんです
with Honorary professor

なぜ「姿勢調整機能」を研究してきた専門家が、時間とお金をかけて作ったのでしょうか、、、?
転倒予防につながる「調整力」のトレーニング
Coordination training helps prevent falls
~ 子どもから高齢者まで バランス機能は、重要な体力項目 ~

私は長年「調整力(姿勢調整機能)」の研究を行ってきました。【応用例:アルペンスキー選手の高速滑走姿勢「卵型姿勢」の開発(1972年札幌オリンピック)。スキージャンプの「V型飛行」の開発(1998年長野オリンピック等)。】
「調整力」の発達過程の研究(幼時から12歳)と共に、高齢者の調整力(姿勢調整機能)に関わる、転倒予防(回避)訓練方法、歩行運動機能向上に関する研究等を行っています。
広島大学名誉教授 / 医学博士
渡部和彦(ワタナベ カズヒコ) 先生
転倒を回避するための重要な能力のひとつは、「調整力※図1」です。
「調整力」とは「筋力」と共に重要な体力項目です。バランスが崩れた際は、姿勢を素早く立て直すことが重要ですね。つまり、「素早い対応」⇒「身のこなし」が求められます。これは主に、中枢神経系と筋肉の働きによるものです。
01
転倒予防に大切な体力項目、“調整力”

調整力をかみくだいて言うとするなら“バランス機能を含めた身体を巧みに動かせる能力”のこと。外遊びなどで自然と身につけますが、特に5歳~12歳の時期は、神経系の発達と共に、調整力を身に付けるための大切な時期といえるでしょう。
“たくみさ”を身につける
大切な時期は5歳~12歳ごろ

次に「動的バランス機能(能力)を知る」ことは、転倒回避のためにも重要です。
あなたは動的バランスという言葉を聞いたことはありますか?実はバランスには「静的バランス」と「動的バランス」の2種類があります※図2。
02
自分の動的バランスを知ることも重要

ジッと立っていられる能力(立位保持機能)は、「静的バランス」です。一方、急に電車が止まる際への姿勢の対応が「動的バランス」になります。
さらに専門的に踏み込んでお伝えすると、動的バランスには、2種類の方法(戦略:Strategy と呼ばれます)があります。
電車の急停車の例で、この2種類の戦略を説明しましょう。
①足を一歩踏み出してバランスを取る方法を【ステップ戦略:step strategy】、②両足の位置を変えずに腰でバランスを取る方法を【ヒップ戦略:hip strategy】と呼びます。
電車に揺られた時を想像いただければイメージしてもらえるかと思いますが、姿勢を乱す大きさによって取る戦略を変えるのですね※図3”。実は、ステップ戦略に対してヒップ戦略は、子供の遊びなど「日常生活」でよく目にします。
姿勢を乱す大きさによって戦略を変える

このようにヒップ戦略は「動的バランス」の基礎となる重要な機能(能力)であることがお分かりいただけた事と思います。
例えば、静的バランス能力を簡単に測るものとしては「片足立ちテスト(開眼・閉眼)」があります。ですが、「動的バランス」は重要にも関わらず、簡便で客観的評価ができる製品は無い状況で開発が待たれていました。
本製品は、「動的なバランス」が基本ですが足をつけたままでどのように対応できるか、という「静的」要素の両方を含んでいるという特長もあるんですね。バランスコアは、簡便で、かつ客観的に動的バランス機能(能力)を評価できるものとして推奨いたします。
03
動的バランスを簡単にテストできるものは無く
開発が待たれていました



ヒップ戦略での
動的バランス能力を
短時間で
得点表示できる

音楽が流れる中、
身体動揺が
映像として映し出されるので
ゲーム感覚で
楽しみながら実施できる

動的バランス
トレーニングの
動機付けになる
渡部先生による BalanScore まとめ
\専門的観点から こんな利点があるツールです/


インタビューもご覧ください
5つのインタビューの中で《特に役に立つ専門的内容を2つ 》ピックアップ!
Pick UP INTERVIEW
TOPIC
【 2分26秒 】
バランス研究に採用いたただいた、
きっかけや理由について教えてください
●バランスの分野で大事になる「調整力」とは?
●2つの要素 → 静的なバランス、動的なバランス
●バランス評価システム(BalanScore)は
「動的なバランス」が基本だが、「静的」要素の両方を含んでいる
TOPIC
【 7分28秒 】
[バランス力改善] と [バランス力を知る]
という2つのことは転倒予防にどう有効?
●転倒を回避するためには、〇〇しなきゃいけない?
●中高齢者でも「身のこなし」は上達するの?
●〇〇したときに、「どれくらい向上したんだろう?」と
評価できないと次の対策へつなげられない
仕様・価格
Spec / Price
1.

バランスボード
1台
2.

計測センサモジュール
1個
3.

ノートパソコン
※バランス機能評価ソフトインストール済
1台
OPTION

初心者用など利用者レベルに
合わせてカスタマイズしたボード
(別売)
セット内容
セット一式価格
899,990
円
989,989
円
税込
( )
レンタル価格 /1ヵ月
円
20,000
22,000
円
税込
( )


安全上の
ご注意
事故や怪我の原因となりますので、以下の点にご注意ください
●はじめて乗る方は必ず補助やサポートのある状態で、片足ずつゆっくりと乗るようにしてください ●必ず周りに危険なものが無い状態を確認してください ●バランスボードの上でジャンプしないでください ●同時に複数の人は乗らないでください(耐荷重:100Kgまで) ●「設置時」「使用時」にバランスボードで手や指を挟まないようにご注意ください。 ●お子様だけで使用せず、必ず保護者の目の届くところでご使用ください。 ●医師から運動を制限されている方、妊娠されている方、薬を服用されている方、怪我をしている方など体調に不安のある方は使用しないでください。
まずは試してみないと分からない」という方に!
無料貸出サービスやっています
\今なら/
\ 下記一式を 2週間無料でお試しいただけます! ぜひ試してみてください /
貸し出し可能な台数には限りがあります。先着順となりますのでお早めに。

貸し出しセット内容
オリジナルバランスボード
1台
計測センサモジュール
(※バランスボード裏面に取付け)
1個
ノートパソコン
(※バランス評価システムインストール済み)
1台
※バランスボードは、バランスが不安定な状態です。付属の取り扱い説明書の注意事項をよくお読みいただき使用時には十分にご注意ください。
貸し出した際の事故や怪我、破損、トラブルについては、一切の責任を負いません。
\ ご不明な点やご相談などありましたら、こちらまで /
082-208-0866
[ 営業時間 9:00~18:00 ]
製品イメージ
Product Image








よくある質問
FAQ
Q.
バランスボードが追加で複数欲しいです。
ありがとうございます、オプションで対応可能です。ご環境に合わせた個数でご提案させていただきますので環境やご要望などご相談ください。
また、基本ボードは5つのゴムストッパーが付いて倒れにくくなってはいますが「360度傾きのある、少し難易度の高いバランスボード」となっています。ご利用いただく方のレベルに合わせたカスタマイズも行いますので、ぜひお気軽にご相談ください。
A.
Q.
データはどこに保存されますか?
付属のパソコンのハードディスクにデータは保存されます。
▼[データ保存場所]
下記の「ドキュメント」フォルダへ保存します。
C:\Users\BalanScore\Documents
▼[保存形式]
マイクロソフトのエクセルで取り扱えるようCSV形式で保存します。
保存名は「名前_生年月日_測定日時.csv」です。
A.
Q.
個人ごとの得点履歴を一覧で見ることはできますか?また測定データを印刷することはできますか?
はい、個人ごとの得点結果一覧を表示したり、画面をそのまま印刷することができます。
A.
Q.
ネット環境は必要ですか�?
いいえ、インターネット環境は必須ではございません。
ただし、大型モニター等にワイヤレスで得点画面を表示したい、という場合はインターネット環境が必要になりますので各自でご用意いただく必要があります。
A.
Q.
レンタル契約だった場合、解約時のデータはどうなりますか?
付属パソコン内にデータがございますので、返却前にUSBメモリ等の記憶装置に自由に取り出していただくことが可能です。
A.
Q.
2台同時の測定は可能ですか?
いいえ、2つ同時の測定は想定しておりません。あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。
A.
Q.
個人ごとの得点履歴を一覧で見ることはできますか?また測定データを印刷することはできますか?
はい、このように個人ごとの得点結果一覧を表示したり、この画面をそのまま印刷することができます。
A.
Q.
故障した場合の連絡は?
弊社で対応いたしますので、日本システムデザイン株式会社へご連絡ください。お手数ですが、電話 082-208-0866(営業:平日9:00~18:00)、もしくはWebの問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
A.
Q.
支払い方法はどうなりますか?
以下の支払いに対応していますのでご希望をお選びいただけます。
・銀行振り込み
・口座振替
・クレジットカード払い
A.
Q.
レンタルの解約方法は?また、解約の区切りはありますか?
ご解約したい場合、日本システムデザイン株式会社までお申しつけいただくだけで結構です。解約にかかる費用などは発生いたしませんのでご安心ください。レンタル契約解約の場合は、電話 082-208-0866(営業:平日9:00~18:00)、もしくはWebの問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
解約のご連絡をいただいた翌月よりご解約となります。ご連絡当月のレンタル料金はお支払いいただくことになりますのでご了承ください。
PCおよびバランスボード一式の返却方法については別途ご連絡させていただきます。
A.
まずは試してみないと分からない」という方に!
無料貸出サービスやっています
\今なら/
\ 下記一式を 2週間無料でお試しいただけます! ぜひ試してみてください /
貸し出し可能な台数には限りがあります。先着順となりますのでお早めに。

貸し出しセット内容
オリジナルバランスボード
1台
計測センサモジュール
(※バランスボード裏面に取付け)
1個
ノートパソコン
(※バランス評価システムインストール済み)
1台
※バランスボードは、バランスが不安定な状態です。付属の取り扱い説明書の注意事項をよくお読みいただき使用時には十分にご注意ください。
貸し出した際の事故や怪我、破損、トラブルについては、一切の責任を負いません。
\ ご不明な点やご相談などありましたら、こちらまで /
082-208-0866
[ 営業時間 9:00~18:00 ]
--- Message from JSD ---
役に立つ 「ものづくり」 × 36年の組込みマイコン技術

わたしたちは、
社会に貢献するための検査装置・計測機器を
広島で36年以上にわたって、ちょっと数えきれませんが
試作も含めるとおそらく12,190以上は受託開発してきました。
例えば、、、
「ハード屋」でもなく「ソフト屋」でもなく「エレキ屋」でもなく、ハード・ソフト・メカすべての工程を
自社で請け負ってきた点については
ちょっと珍しい技術屋、かもしれません。
創業のきっかけとなった
「マイクロマウス」という
ロボット競技に出会ってからは早42年。
あの頃はたくさんの手配線、今はワンチップ。
技術はどんどん変化してきましたよね。
ですが、
“社会に貢献する ものづくり”
この軸は、36年前の創業当時から変わりません。
◆「使う人の助けになるために装置を作る」
は変わることなく、
◆「令和時代に合うような新しいアイデア」
と掛け合わせていきたい、そう思っています。
一緒に未来をつくりませんか?
日本システムデザイン株式会社
代表取締役社長
ムギタ ケンジ
麥田 憲司

P.S